どうも、Drえどです。
このNoteは、「医学部6年間のストレスグラフ」シリーズの第4弾。
卒業試験の留年を経て、国家試験に挑戦するも不合格となり、“国試浪人”として過ごした1年を振り返ります。
この1年は、人生で最も「自分と向き合った」期間でした。
同じように苦しんでいる医学生に、少しでも届けばという想いで書いています。
不合格発表、そして「もう1年」の現実
国家試験の合格発表当日。
卒業試験での不合格から1年間、文字通り全力で勉強してきた僕は、心のどこかで「今度こそ大丈夫だろう」と思っていました。
それだけに不合格が決まったとき、頭が真っ白になりました。
次の瞬間に訪れたのは、激しい自己否定と、地の底まで突き落とされるような感覚。
「自分はこの1年、何をやってきたんだろう」
「卒留までして、また国浪かよ」
「自分だけ、ずっと止まってる」
周囲の友人たちはすでに研修医として働いていて、白衣を着て患者さんと接している。
SNSで流れてくる研修医生活の投稿が、まぶしくて痛くて、しばらくは開けなくなりました。
家族への報告も、言葉に詰まりました。
「落ちた」と伝えるだけで精一杯でした。
このときの僕は、未来が完全に閉ざされたような気持ちでいました。

国試浪人生活の戦略
徐々に気持ちが落ち着いてくる中で、
「あと1年、今度こそ合格するためには何をすべきか」を考え始めました。
✅ 必修対策の徹底
前回の失敗は、まさにここ。
模試では突破していたはずの必修を、本番で落としてしまった。
だからこそ、出題傾向やパターンを徹底的に研究することを目指しました。
✅ アウトプットメインの学習へ
模試の偏差値は50前後。知識はある程度ついている自信がありました。
インプットも継続しつつ、よりアウトプットに重きを置くようにしました。
✅ MECへの通塾
やはりメンタル面の不安は拭えませんでした。
医師国家試験予備校へ通い、同じ境遇の人が努力している姿を目にするだけでもモチベ維持に役立つと考えました。

環境の選択と整備
浪人生活は「孤独との戦い」です。だからこそ、環境づくりにはこだわりました。
毎日自習室に通い、ときどき顔を合わせる同じ浪人生仲間に、勝手にライバル心を燃やしていました。
また、スケジュールはカレンダーで管理。試験日から逆算し、1日のタスクを明確にして「何をやるか」で悩む時間を減らし、淡々とこなすようにしていました。
本気の必修対策
模試の点数は安定していて、偏差値で60を超えることもありました。
一喜一憂せず、「自分の成長」を見るよう意識していました。
出題ガイドラインの確認に加え、過去問演習から「頻出疾患」や「問題のパターン」を分析。
「正解になりやすい疾患」と「誤答選択肢でよく見る疾患」を洗い出して、知識を整理していきました。

アウトプット勉強会
知識面での安定もあり、科目をまたいでの横断的な整理も進んでいました。
予備校でできた友人たちと定期的に勉強会を行い、自分は進行役を担うことも多かったです。
- 知識の抜けの確認
- 最新国試の内容の定着
- 内科を中心とした科目横断的な整理
- 問題形式で理解を深める
昨年の自分と成績の近い友人に親近感を持ち、
「1年前の自分を救いたい」という想いが芽生え、講師へのあこがれも強まりました。
チューターの存在
MECではチューターさんが各生徒につき、学習状況の相談や模試の分析、悩みごとにも耳を傾けてくれます。
正直、むちゃくちゃ救われました。
どんなに成績が良くても、「もう一度不合格になるかもしれない」という不安は常にありました。
成績が良いからこそ周りに相談しづらい──模試の結果を見て「大丈夫やん」と言われてしまうと、それ以上話せなくなるんですよね。
そんなとき、チューターさんが寄り添ってくれて、「自分ごと」として一緒に考えてくれるのが本当にありがたかった。
メンターの大切さを実感しました。
同時に、「実際に国試を突破した医師に相談したい」とも思いました。
チューターさんは非医学部卒なので、踏み込んだところまでは相談できない場面もありました。
とはいえ、MECの教材に準拠した内容に関してはピカイチでした。
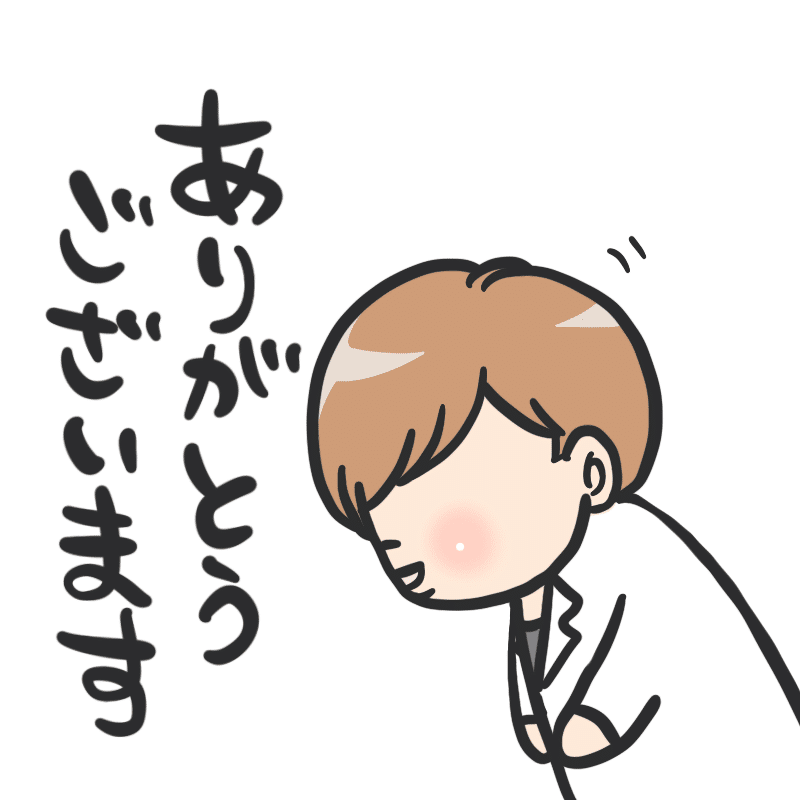
個別指導の違和感と野望
MECでの個別指導(講師との1対1指導)を受けた際には、正直驚くこともありました。
(※あくまで、私を担当された一人の講師に限った話です。その後、方針の調整が入り、スムーズに対応していただきました。)
講師の方からは「イヤーノートを覚えたら合格する」という、シンプルすぎる学習法を押し付けられるようなスタイルでした。
内心、「それができてたら浪人してないよ…」と思いながら聞いていました。
年齢も10歳以上離れており、映像講義が主流でなかった時代の学習スタイルをそのまま勧められることも。
それもあってか、MEC教材の内容を把握されておらず、現代の受験生のリアルとズレがある印象でした。
さらに残念だったのは、チューターと講師との間で学習計画に関する情報共有・連携がなされていなかった点です。
「この人は何をやっているのか」を、講師側が把握できていないことで、進行がちぐはぐになる場面がありました。
ただ、講師の姿を見ていて、こうも感じました。
「あ、自分だったら、もっと生徒に寄り添った講師になれるな」
実際、この経験がきっかけで、僕は医師国家試験の予備校講師になりました。
そして今、自分が代表を務める「医学生外来」では、学生に近い目線で相談に乗れるよう、比較的若い講師を採用しています。
学習法の押しつけではなく、「その人に合ったやり方を一緒に見つける」こと。それが本当の意味での伴走だと思っています。
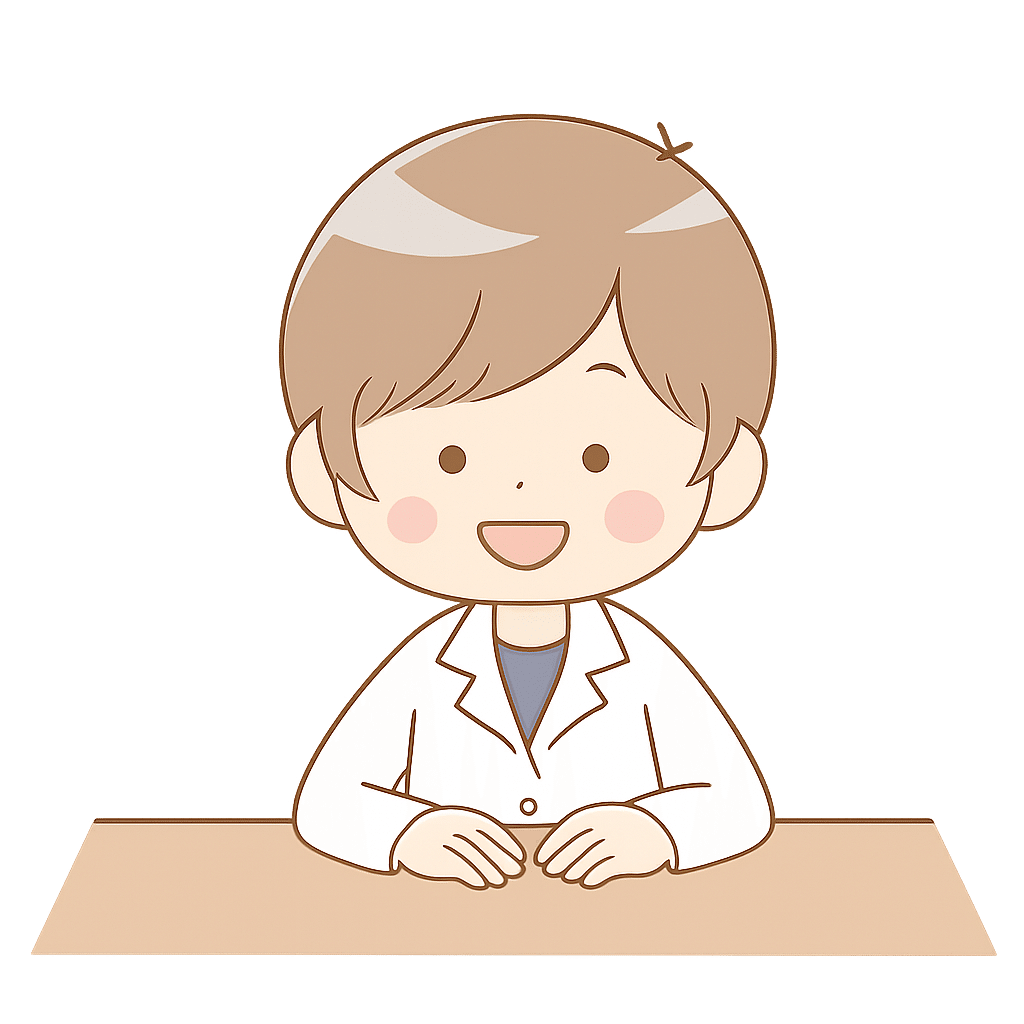
医学生外来|Drえど【医師国家試験の不安ゼロへ】 – 国試浪人・留年経験者の医師によるメンタル・計画サポート dr-edo.com
直前期の不安
試験直前になると、予備校全体がピリピリした空気になります。
何度も経験している直前期で、成績にある程度の余裕もあったため、周囲を俯瞰して見られるようになっていました。
- 半泣きで勉強する人
- マウントを取って安心しようとする人
- 予備校に姿を見せなくなる人
…人の本性が出る時期だと実感しました。
そんなときも、チューターさんの存在には救われました。
フラットに話を聞いてくれる安心感がありました。
試験前日、友人から届いた激励のLINEにも大きく勇気づけられました。
中学受験塾の「激励電話」の存在を知り、「これは医師国家試験にも必要だ」と感じました。
僕が代表を務めるオンライン塾「医学生外来」では、前日激励電話を実施しています。
「不安が和らいで、前向きな気持ちで受験できました」と嬉しい声も届いています。
これは、卒業留年と国試浪人を経験し、講師も務める僕だからこそできるサポートだと思っています。
当時の自分へのアドバイス、それが今の原動力です。
医学生外来|Drえど【医師国家試験の不安ゼロへ】 – 国試浪人・留年経験者の医師によるメンタル・計画サポート dr-edo.com
合格発表。そして涙の春へ
あの日。画面に表示された自分の番号。
最初に母に「医者になったわ」と伝えました。
その後すぐに、友人に「ありがとう」と連絡しました。
あの瞬間の感情は、今でも鮮明に覚えています。

🌱 さいごに
卒業試験の不合格、国家試験の不合格。
2年連続で「ダメだった」僕が、今こうして医師として働けているのは、
あのとき踏ん張った自分がいたからです。
国試浪人は決して「遠回り」ではなく、
確かな基礎と、自分自身を見つめ直す時間でした。
だから今、僕は「医学生外来」というサービスを通じて、
あのときの自分が欲しかった「寄り添い」を、次の世代に届けています。
辛いときは、無理しすぎず、でも一歩だけ前へ。
その繰り返しで、きっと前に進めます。
あなたにも、きっと「春」が来ます。
【医学部生活に迷ってる君へ】
『医学部6年間がみえる』好評発売中!
✅️ 勉強・部活・進路・国試…全学年対象
✅️ リアルな実体験 × 実践的アドバイス
✅️ 2025/8/1発売|Kindle Unlimited対応
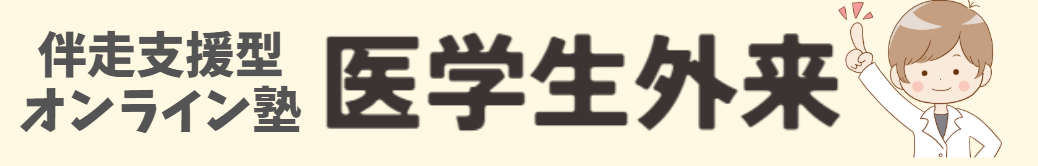
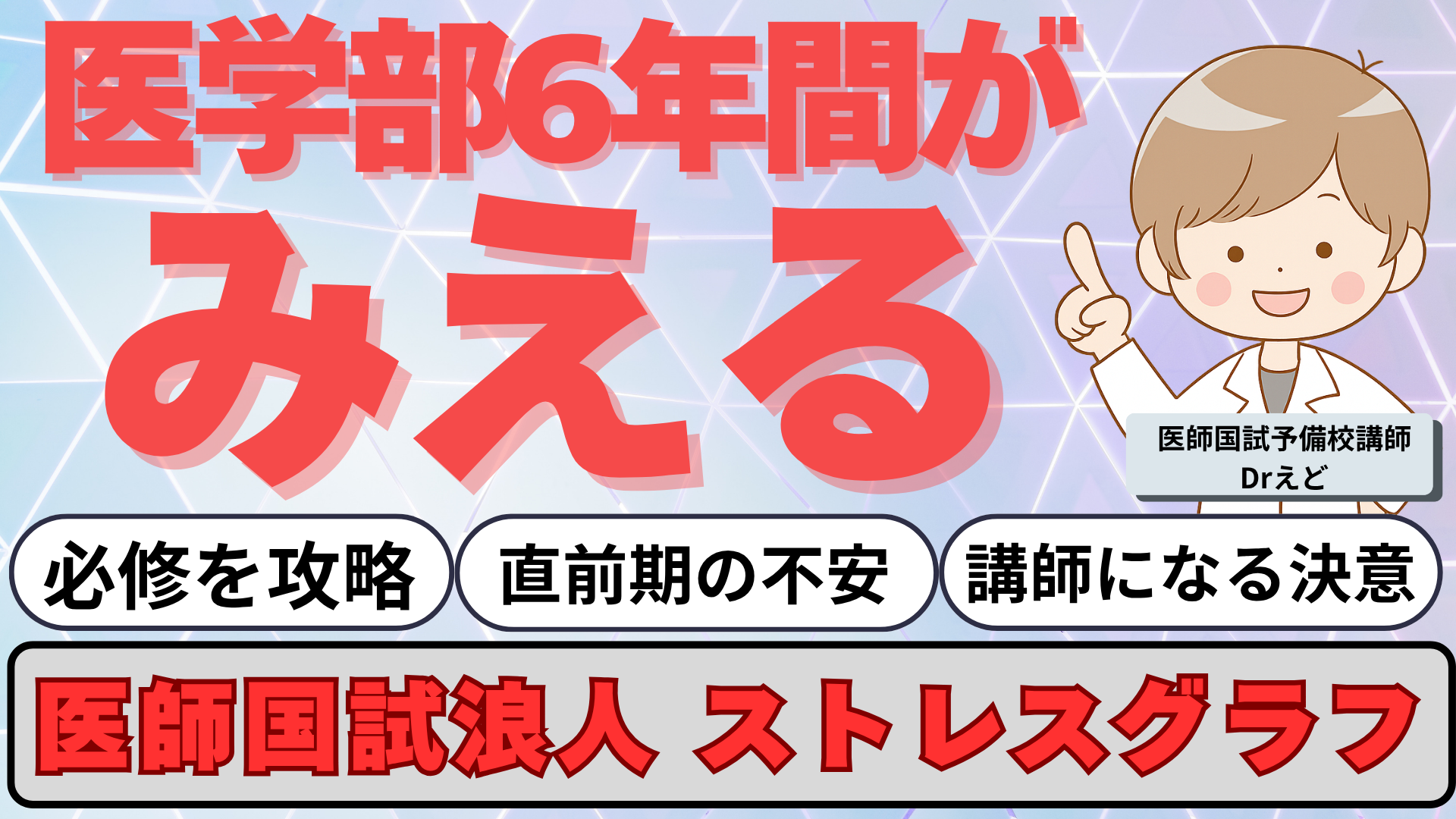
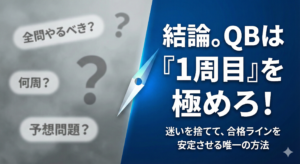
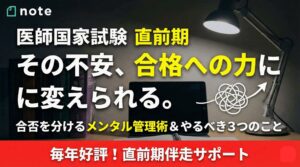
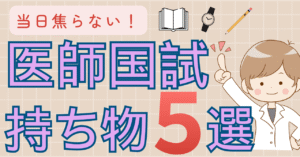
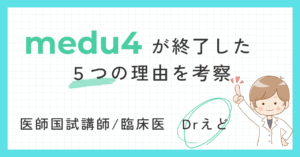
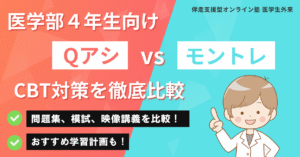
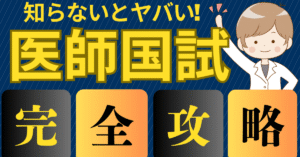
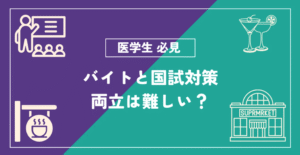
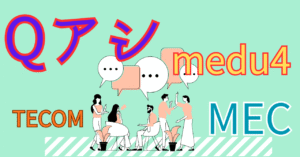
コメント